思わずきゅんとしてしまう妄想ツイートが大人気!
今話題のライター・編集者のカツセマサヒコさんに雌ガールのための恋愛小説を書いてもらいました。
記念すべき第一回目は青春時代を振り返る砂糖菓子みたいなあまーい恋。
ときめきと共感が止まらないカツセワールドをご堪能あれ♡
誰だって一度や二度、いや三度、四度と恋をする。
わたしもご多分に漏れず、27歳にして、三度目の恋に落ちた。
これまでの恋を振りかえってみると、「イエーイ! 最高! これっぽっちも忘れらんない!」と手放しで喜べるものばかりではなかったし、むしろ後悔した点もある。
でも、どの彼氏とも、人並みに充実した時間を過ごしてきたつもりだ。とくに、最初の恋人とのそれは、とにかく甘くて純粋で、なんだか綿菓子みたいな恋だった。
+++
「上里さんのことが、好きです!」
ショートパンツすら穿いているのが億劫になるほど、暑い夏の夜。連絡先を聞いたその日のうちに、個別指導塾の教師である彼に、そう送った。
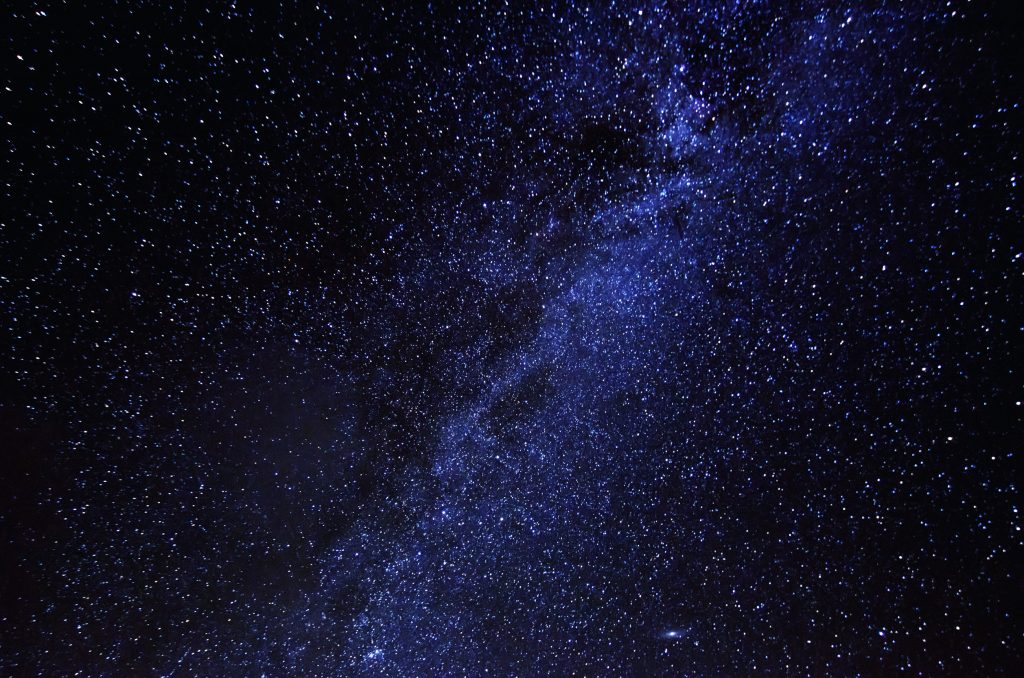
とにかくタイプだった。黒髪のクセ毛はワックスも付けていないのに自然と馴染んでいるし、「大学生」というブランドがめちゃくちゃ似合うオトナっぽさがあったし、笑うと目がなくなる奥二重が最高すぎてヤバい。彼が笑顔になるたび、わたしのなかのトキメキ中枢のようなモノが激しく脈打つので、お笑い事務所にでも入って彼を笑わすことに生涯捧ぐのも悪くないと思えた。
受験シーズンを控えた大事な時期だったけど、友人に携帯を見せながら「ねぇこれ見てよ、アイス食べてんの。大学生だよ? かわいすぎじゃない??」と意味不明な自慢をしていたことしか、覚えていない。
+++
「晶はすぐに諦める。“諦めのアキラ”だ」
ファミレスで英語を教えてもらっていると、彼はそう言って、わたしのことをよくからかった。実際、わたしは過去完了形すら理解できていなかったし、集中力がなく、諦めの早い女だった。
「うーるさい。トシの教え方が、ヘタなんだ」
わたしと上里俊之は、あの日から教師と生徒という関係をあっさりと飛び越え、付き合うことになった。憧れの人が自分の彼氏だなんて、この人より後には起こらなかった。当時はもう図に乗りまくっていて、友人と遊ぶ時間や勉強時間を削ってでも、トシとの時間に費やしていたかった。
+++
わたしが東京にある第二志望の大学に受かると、トシは一泊二日の慰安旅行に連れて行ってくれた。
「晶は、何が飲みたい?」
「ココア」
「ホンっト子どもな」
「子どもと付き合ってるロリコンおじさんに、言われたくないなあ(笑)」
「うっわ、それ、意外と刺さる」
いつもトシとドライブに出かけるときは、自宅の横にある自販機で飲み物を買ってから車に乗るのがルールだった。その時間も好きだったし、なにより、運転席に座る彼は、ただひたすらかっこよかった。
「バック駐車のときに手を置くやつがヤバい」とか、そういうわざとらしいシーンじゃない。「ウインカーを付けるための指の動きひとつひとつがセクシーすぎて発狂する」というレベルだった。信号機が赤になるたびキスしたくなる衝動に駆られ、とにかく落ち着きのない助手席の時間を過ごした。
「受験が終わるまで我慢」がお互いの口癖だったわたしたちは、これまで禁じてきたすべてのことを、この旅行で解禁した。
まだ日も暮れぬうちから抱き合って、彼のほっそりとした鎖骨、薄い胸板、熱い吐息に、初めて触れた。くっつけばくっつくほどハッキリする彼とわたしの境界線が、なんだかもどかしくも心地よく、彼の全てを欲しくなった。
このまま、時が止まればいい。本気でそう願った。あのときのわたしたちは、まぎれもなく、世界でいちばんの恋をしていた。

トシとの関係が冷めだしたのは、わたしが晴れて大学生となり、周囲の環境がガラっと変わっていったころからだ。サークルや授業が忙しくトシへの返事が遅れがちなことが続くと、彼はどんどん不機嫌になり、そのうち、彼からの連絡の方が遅くなっていった。
わたしはわたしで、重いオンナにはなりたくないと思っていても、彼のレスポンスが悪ければ悪いほど束縛を強め、ヒマさえあれば彼のSNSアカウントを片っ端から覗き、そこに投稿されているのにわたしへの返信がないと、そのことにいちいち腹を立て注意することが増えていた。
「もう、ダメかもしれない」
そう頭ではわかっていても、これまで過ごした日々が失われ、トシの体温を感じられなくなるのは、絶対に避けたかった。
初デートで山の展望台から見た、田舎ならではのポツポツとした寂しい夜景。レストランが予約できていなくて、隣のファミレスで笑いあったクリスマス。横になったベッドから眺めていた、雲ひとつない空と波の音。
すべてが、過去になろうとしている重圧に、ただただわたしは落ち込むばかりだった。

「ごめん」
別れ話を切り出されたのは、1ヶ月半ぶりのデートを終えて家まで見送ってくれた、その後だった。
理由は、なかった。ただわたしは大学生となり、彼は就活が始まった。わたしたち自身は何ひとつ変わっていないつもりだったのに、環境が変わっただけで、いつの間にか、気持ちが離れてしまっていた。
「いつから?」
「もう戻れない?」
妥協点を探そうと尋ねても、ただただ機械のように、彼は謝り続けた。
その日はもう食い下がることもできなくて、帰ってからシャワーを浴びながら、泣いた。次の日も、その次の日も、付き合った当初のふたりを思い返しては、涙が出た。何か伝えようと思ったのは、別れた3日後だった。
「“諦めのアキラ”にだって、諦められないことぐらいあるよ」

20歳になったわたしでも、別れを切り出されたときに言えるユーモアは、そのぐらいだった。ツイッターにそれを投稿すると、2日後に「いいね」が付いて、終わった。
20歳の冬、わたしの人生でいちばん輝いていた恋が、この生涯でもっとも諦めたくなかった恋が、終わりを告げたのだった。
【中編ヘ続く】
Text/カツセマサヒコ
下北沢のライター・編集者
Twitter: @katsuse_m
































